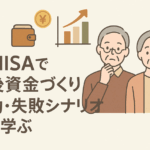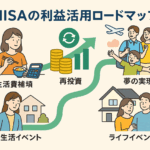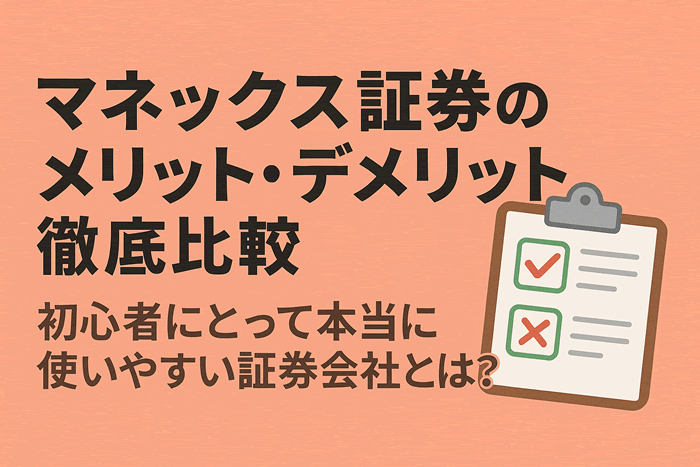
マネックス証券が気になっているけど、「他の証券会社と比べてどうなんだろう?」と迷っていませんか?
ネット上には「米国株に強い」「分析ツールが豊富」といった声がある一方で、「アプリが見づらい」「サポートがいまいち」といった意見もあり、判断が難しいのが正直なところです。
この記事では、マネックス証券を使ううえでの具体的なメリット・デメリットを、初心者にもわかりやすく整理。
SBI証券や楽天証券といった主要ネット証券と比べながら、どんな人にとってマネックスが合っているのか、逆に向いていないのはどんな人かも丁寧に解説します。
筆者自身も「どこで口座を作るか」本気で悩んだ経験があります。だからこそ、“自分の投資スタイルに合う証券会社”を選ぶための視点を、できる限りフラットにお伝えしていきます。
この記事を音声で聞きたい人は再生してみてください↓
こんな人がこの記事にたどり着いていると思います
「マネックス証券、気になるけど…」
この記事を読んでいるあなたも、そんな風に感じているのではないでしょうか。
すでに口座を持っている人の声や、ネットの評判をいろいろ調べて、ある程度の情報は手に入れた。
でも——
「他の証券会社とどう違うの?」
「デメリットもちゃんと知ったうえで判断したい」
「結局、自分にはどれが合ってるのか分からない…」
そんな“モヤモヤした状態”で立ち止まっている方にこそ、この記事は読んでいただきたいと思っています。
証券会社の選び方には、「絶対的な正解」なんてありません。あるのは、“自分のスタイルに合うかどうか”という視点だけです。
けれども、ネットには断片的な情報や、極端な意見も多く、どれを信じればいいのか分からなくなるのも無理はありません。
この記事では、筆者自身が実際に悩み、比較し、試してきた中で感じたことも交えながら、マネックス証券のメリット・デメリットをフラットに解説していきます。
「いいことばかり書いてある公式サイトとは違う、“等身大の比較”」として、あなたの判断の材料になればうれしいです。
マネックス証券の強み(メリット)をリアルに整理してみた
ネット証券はどこも似ているようで、実はそれぞれ得意分野が異なります。
マネックス証券にも、他にはない強みがいくつかあり、それが一部の投資家に熱く支持されている理由でもあります。
ここでは、筆者自身が「なるほど、これは使ってみたい」と思えたポイントを中心に、初心者目線でわかりやすく整理してみます。
米国株に強い|取扱数・注文機能・情報量すべてが充実
マネックス証券の一番の強みは、米国株に対する圧倒的な対応力です。
SBIや楽天と比べても、取扱銘柄数や注文の自由度、企業情報の豊富さはトップクラス。
📌 特徴まとめ:
- 取扱銘柄数は5000以上(2025年時点)
- 時間外取引や逆指値注文にも対応
- 米国企業の決算データや財務分析レポートが見やすい設計
- 為替スプレッドが比較的狭く、手数料も割安な部類
💬 筆者の感想:
米国株を調べていて、「あれ、この企業、SBIや楽天では買えないのにマネックスでは買えるんだ…」ということが何度かありました。
“米株を本気でやりたい人”にとっては、選択肢の幅広さは大きな武器になります。
クレカ積立で1.1%ポイント還元|実は生活に役立つ裏ワザ
マネックス証券では、「マネックスカード」を使って投資信託を積み立てると、毎月の積立額に対し1.1%分のポイントが還元されます。
クレカ積立の主な特徴:
- 投資信託の積立上限:5万円/月(他社と同等)
- 還元率:1.1%(2025年時点)と業界最高水準
- もらえるポイントは「マネックスポイント」→ Pontaやdポイントに交換可能
💬 筆者の視点:
正直、「積立にポイント?なんとなくお得そうだけど…」くらいに思っていました。でも実際、月5万円×12ヶ月×1.1%=年6600円分のポイントが貯まると考えると、これは無視できない差になります。
分析ツールのレベルが高い|MONEX VISION β、銘柄スカウターなど
他の証券会社よりも「情報をしっかり提供してくれる」という印象を強く持ったのが、マネックス証券の投資分析ツールの豊富さです。
📊 主なツール:
| ツール名 | 特徴 |
|---|---|
| MONEX VISION β | ポートフォリオ全体の将来予測をシミュレーション可能 |
| 銘柄スカウター | 個別企業の10年分業績推移や指標比較をグラフ表示 |
| 米国株銘柄スカウター | 決算速報、ROE、売上成長率などの視覚化が容易 |
💬 筆者コメント:
「自分で調べて納得して買いたい」という人にとって、これらのツールは本当にありがたい存在です。
特に銘柄スカウターの10年業績グラフは、株式初心者に“見る力”を育ててくれると感じました。
教育コンテンツが豊富|動画・セミナー・メール講座など
初心者にとって、証券会社を選ぶ上で大事なのは「スタート後の学びやすさ」でもあります。
マネックス証券は、その点でも“育ててくれる環境”が整っている証券会社です。
📚 提供されている学習コンテンツ:
- 投資初心者向けの動画セミナー(ライブ&アーカイブ)
- メール講座(NISA・投信・株式などテーマ別)
- マネユニ・アカデミー(マネックスが提供する学習ポータル)
実際にマネックスの教育コンテンツを使っている人のレビューをDMで頂いた事があります。
NISAの仕組みやメリット・デメリットを、図解付きで丁寧に教えてくれるメール講座が思った以上に分かりやすかったです。最初に読んだとき「もっと早く知りたかった…」と思いました。
マネックスの初心者セミナーは「基礎の基礎」から教えてくれる感じで、金融の知識に自信がなかった私にもすんなり入ってきました。しかも無料でアーカイブ視聴できるのは本当にありがたい。
証券口座を開いたあと、次に何をすればいいか分からなかった私にとって、週1で届く学習メールが“頼れるガイド”のようでした。機械的じゃない説明文で、読んでいて安心感がありました。
動画セミナーでNISAや投信について学べたおかげで、「とにかく始めてみよう」と踏み出す決心がつきました。講師の方も初心者目線で話してくれて好印象でした。
気になるデメリットも正直に書いてみる
どんなに魅力的なサービスでも、当然ながら完璧ではありません。
マネックス証券にも、実際に使ってみて「ここはちょっと気になるかも…」と感じたポイントがあります。
でも、それをあえてここで正直に書いておくことで、読者の方に「信頼できる記事だ」と思ってもらえるなら、本望です。
アプリの操作性はやや“クセあり”|慣れるまでは戸惑う人も
SNSの口コミでも多かったのが「アプリが分かりにくい」という声です。
マネックスのアプリは用途別に複数用意されていて(例:株アプリ、投信アプリなど)、その切り替えや構成が最初は少し直感的ではないと感じる方も多いようです。
⚠️ 実際の困りごと例:
- 投信は「マネックス証券アプリ」ではなく「マネックス証券 投信アプリ」からの操作になる
- ログイン後の画面構成がやや情報過多で、「どこから操作すればいいか迷う」ケースも
💬 筆者の感想:
私も最初は「え、これはどのアプリを使えばいいんだろう?」と少し混乱しました。ただ、数日触ってみると構造が分かってきて、今では逆に“目的別に分かれていて使いやすい”と感じるようになりました。
サポート対応は“淡白”に感じることも|丁寧さより効率重視?
もうひとつ、口コミで時折見かけるのが「問い合わせに対する対応が事務的だった」「返答まで時間がかかった」という声です。
📌 具体的に言われている内容:
- メール返信に1~2営業日かかる
- テンプレ回答が中心で「人間味が薄い」と感じる
- 電話サポートは混雑してつながりにくい時間帯も
💬 筆者の見解:
個人的には、問い合わせを多用する使い方でなければ、それほど大きな問題には感じませんでした。とはいえ、「安心感」や「対人サポートの手厚さ」を重視したい人には、やや物足りない部分かもしれません。
IPOや信用取引を積極的にやりたい人にはやや不向きかも
マネックス証券は、米国株や長期投資に強い反面、IPO(新規上場株)や信用取引に関してはやや弱めという印象があります。
📉 他社との比較ポイント:
| 項目 | マネックス証券 | SBI証券 |
|---|---|---|
| IPO銘柄の取扱数 | 少なめ | 業界最多クラス |
| 信用取引の手数料 | 標準的 | 割引制度多数 |
| IPO当選率 | 抽選方式(完全平等) | 当選本数多いが競争激化 |
💬 筆者のコメント:
IPO目的で口座を開くなら、SBI証券の方が有利な面があるのは事実です。ただし、マネックスも抽選方式は“完全平等”なので、少額投資家でもチャンスはあります。
🤝 バランス視点:デメリットは「許容できるか」で判断するのが正解
どれも“致命的な欠点”というよりは、「どんな投資スタイルか」によって印象が変わる部分だと私は感じました。
たとえば:
- 長期投資&米株中心 → アプリの構造は気にならない
- サポートを頻繁に使う想定がない → 淡白でも問題なし
- IPOは年に1〜2回応募できればOK → 十分対応範囲
何を重視するかによって、同じデメリットが「問題」にも「気にならないこと」にもなる。
それを見極めることが、証券会社選びで失敗しない最大のコツだといえます。
実際にどんな評判があるのか、SNSや口コミをもとにリアルな利用者の声を集めた記事もご用意しています。
他のネット証券との違いをやさしく比較
証券会社選びに悩んでしまう理由の一つは、「比較しても、どれも一長一短に見える」こと。
でも実はそれって、ある意味で正解なんです。なぜなら、どんな証券会社にも“得意なこと”と“ちょっと弱いところ”があるから。
ここではマネックス証券と並びよく比較される「楽天証券」「SBI証券」の2社と比べながら、初心者が迷わないように、“感情を交えたやさしい比較軸”で整理してみます。
マネックス vs 楽天証券|シンプルさと生活連動の強さが楽天の魅力
| 比較ポイント | マネックス証券 | 楽天証券 |
|---|---|---|
| クレカ積立の還元率 | 1.1%(マネックスカード) | 0.5〜1.0%(楽天カード) |
| アプリの直感性 | やや複雑(慣れが必要) | 初心者でも分かりやすい構成 |
| ポイント連携 | 独自ポイント → Ponta等に変換可能 | 楽天経済圏と直結(使い勝手◎) |
| 教育・分析ツール | 銘柄スカウターなど高機能 | 最低限の情報、ややシンプル |
💬 感情ベースの比較印象:
- 「はじめて投資するなら、楽天の“やさしさ”は安心」
- 「でも、学びながら続けたいなら、マネックスの“情報の厚み”は魅力的」
マネックス vs SBI証券|全方位の強さ vs 専門特化の深み
| 比較ポイント | マネックス証券 | SBI証券 |
|---|---|---|
| IPOの取り扱い数 | やや少なめ | 業界最多クラス |
| 信用取引 | 標準的 | 手数料・金利優遇など制度が多い |
| 米国株の情報量 | 分析ツール・ニュース豊富 | 実用面で十分だがややシンプル |
| サポート体制 | 淡白/オンライン中心 | 電話・チャット・メール充実 |
💬 感情ベースの比較印象:
- 「がっつりIPOや信用取引に挑戦したいなら、SBIの“プロ感”は安心」
- 「でも、米株や分析に強くなりたいなら、マネックスの“育ててくれる感”がありがたい」
“どっちが上”ではなく、“どっちが合うか”が答え
この比較で伝えたいのは、「SBIや楽天よりマネックスが上」という話ではありません。
大切なのは、“あなたの投資スタイルや目的に合っているか”という一点だけ。
🟨 視点の例:
- 家計の延長線上でコツコツ投資 → 楽天の経済圏を生かすスタイルもアリ
- 本気で米国株に取り組みたい → マネックスの銘柄選定力と情報量が活きる
- IPO/信用メインで動きたい → SBIの制度と環境が有利
💬 筆者の補足:
私自身、「比較記事」をたくさん読んで混乱した側の人間です。
でも最終的にマネックスを選んだのは、「情報がしっかりあって、地に足のついた判断ができそうだ」と感じたからでした。
“自分の性格や目的に合っている”——それが、証券会社選びの一番の納得ポイントになると思っています。
どんな人にマネックス証券はおすすめか?
ここまでマネックス証券のメリット・デメリット、他社との違いを見てきて、
「なんとなく良さそうだけど、自分に合ってるかどうかはまだ分からない…」
という方もいるかもしれません。
そこでこの章では、実際にマネックス証券が“フィットしやすい人”と“やや相性が分かれる人”を、タイプ別に整理してみます。
当てはまる項目があれば、きっとあなたの判断材料になるはずです。
マネックス証券と相性の良いタイプ
💡 米国株投資に本腰を入れたい人
→ 取扱銘柄の多さ、情報量、注文機能の多彩さ。米株に本気で取り組みたいなら安心の環境。
💡 “調べて納得してから買いたい”タイプの人
→ 銘柄スカウターやMONEX VISION βなど、分析ツールの豊富さが知的欲求を満たす。
💡 学びながら投資を進めたい人
→ 教育コンテンツやセミナーが充実していて、“受け身の学習”から一歩進める設計。
💡 クレカ積立×ポイント還元で家計と連動したい人
→ 1.1%という高還元率は、実は家計にとって地味に大きなプラス。
💬 筆者の体験:
「なんとなく投資を始めたい」ではなく、「ちゃんと理解して進めたい」と思ったとき、マネックスの“情報とサポートの濃さ”はかなり頼りになりました。
特に、ツールを通して自分の判断軸が育っていく感覚があったのは、他にはない経験です。
逆に、こういう人は他社も検討してみてもいいかも
⚠️ 「スマホ1つで直感的に完結させたい」タイプの人
→ アプリの構成に多少慣れが必要なため、楽天証券の方がスムーズに感じるかも。
⚠️ IPOを積極的に狙っている人
→ SBI証券の方が取り扱い銘柄が多く、当選チャンスも多い。
⚠️ 対面や電話サポートに重きを置く人
→ マネックスは基本的にオンライン完結型。電話でじっくり話すスタイルを求める人にはやや不向き。
“迷っているなら、とりあえず使ってみる”もアリな選択肢
証券口座の開設は無料ですし、使わなければ費用も発生しません。
つまり、「とりあえず開設して、使い勝手を比べてから本格利用を決める」というのも、今の時代に合った賢い選び方です。
📌 小さなアクションが、大きな選択につながることもあります。
“動いてみることでしか得られない感覚”って、確かにあるんですよね。
迷っている方へ:証券会社選びで大切なのは「情報のバランス感覚」
ここまで読んでくださった方は、きっと「慎重に、でも前向きに」証券口座を選びたいという気持ちを持っているのではないでしょうか。
そしてそれは、とても健全で、正しいスタンスだと私は思います。
投資はお金が絡むことだからこそ、不安になるのは当たり前。
だからこそ、ネットの情報に振り回されすぎず、“自分に必要なものは何か”という軸で選ぶことが、後悔しないための第一歩です。
ネガティブ情報は“声の大きさ”で誇張されやすい
SNSや口コミサイトでは、ネガティブな情報の方が目立ちます。
でもそれは「使っていて不満を言いたくなる人の声」が表に出やすい構造のせい。
📌 覚えておきたいポイント:
- 問題がなかった人ほど、わざわざ何も書かない
- 一部の意見が、あたかも“全体の印象”のように見える
- でも実際に使ってみると「想像より良かった」というケースも多い
💬 筆者の補足:
私自身、「悪い評判が気になって躊躇したこと」もあります。
でも振り返ってみると、それは自分の判断軸がまだ整っていなかっただけだったんですよね。
一社に“完璧”を求めすぎないことも大事
どんな証券会社も、全員にとって完璧な存在ではありません。
大切なのは、「自分が何を大事にしたいか」「どこまでなら妥協できるか」というバランス感覚。
たとえば:
- クレカ積立で日々の生活と連動させたい → マネックスは魅力的
- 分析しながら納得して買いたい → 情報ツールの豊富さが心強い
- でも、シンプルなアプリがいいなら楽天が合うかも…など
📌 完璧を求めるより、“自分にとって納得できる選択”を意識してみてください。
✍️ 筆者のひとこと
私がはじめて証券口座を選んだときも、「ここで本当にいいのかな…」と何度も検索しました。
でも、情報を集めすぎて疲れてしまったとき、最後に背中を押してくれたのは「自分で一歩踏み出すしかない」っていう感覚でした。
そして実際に動いてみたら、「あれ?思ったより分かりやすいし、悪くないかも」と感じられることが多かったんです。
だからこの記事が、あなたにとってそんな一歩のきっかけになれたらうれしいです。